『金融リテラシー入門[基礎編]』より一部抜粋
(本記事は、幸田 博人氏、川北 英隆氏の編著書『金融リテラシー入門[基礎編] 』=きんざい、2021年1月13日刊=の第5章序論(幸田博人/福本勇樹著)の中から一部を抜粋・編集しています)
目次
資産形成の考え方
資産形成では、将来の自分のライフプラン(例:退職後にどのくらいの収入が得られ、またどのくらい長生きして、どのくらい生活費がかかるのか)を想定したうえで、事前にいかにして備えておくのかという観点が重要になる。
また、結婚出産や進学、退職などのライフイベントを経て、当初予定していたライフプランに齟齬が生じた場合は、それに応じて資産形成のやり方も柔軟に見直していく必要がある。
資産形成を行ううえでまず投資家が考えるべきことは、どの程度の「期待収益率」を必要としていて、どの程度の「リスク」までなら許容できるのかという問題である。
○期待収益率
期待収益率とは、ある金融商品を購入したときに期待できる収益(平均値)のことである。主に年率で計算することが多い。
○リスク
リスクとは、期待収益率から乖離する「可能性」のことを指す。すでに支払うことが確定している手数料などの費用はリスクには含まない。
一般的にはリスクが大きい金融商品ほど期待収益率が大きくなる。一方で、リスクが大きくなればなるほど、将来にわたって実際に得られる収益が期待収益率から大きく乖離する可能性も高まる傾向がある。
将来得られる収益が期待収益率から乖離する原因はさまざまあるが、たとえば以下のようなものがリスクとして考えられる。
- 価格変動リスク(市場リスク)……将来、株価、金利や為替相場が変動することで金融商品の価格が変動する可能性のこと
- 信用リスク……債券や株式を発行している発行体(国、地方自治体、企業など)や、間接金融型の金融商品の販売元(銀行や保険会社など)が倒産するなどして、投資元本や利息などの全額もしくは一部が受け取れなくなる可能性のこと
- 流動性リスク……金融商品を市場等で売却したい場合にすぐに売ることができない、または希望した価格で売却できない可能性のこと
資産形成に分散投資や長期投資が求められる理由
資産形成では将来のライフプランにおいて必要な生活資金を想定するなど投資目的を明確化したうえで、現在投資可能な余剰資金と今後の出費予定、貯蓄可能額等を想定し、目標とする収益率または金額を定め、それに合致する適切な金融商品を選択する必要がある。
しかしながら、価格が変動するような金融商品を購入した場合、短期的には必ずしも期待収益率どおりに収益を得られるとは限らない。
基本的に金融商品の期待収益率が高いほどリスクは大きくなるのが一般的である。資産形成では自分自身が許容できる損失の範囲(リスク許容度)を考慮しながら、その範囲で期待収益率の高い金融商品を選択していく必要がある。
そのために、分散投資、長期投資、時間分散などの考え方を理解したうえで活用し、うまく金融商品を組み合わせていくことでリスクを低減させ、目標とする中長期的な期待収益率を達成していくことが重要である。
分散投資を行うことで、個々の金融商品の一時的な期待収益率以上の収益で他の金融商品の期待収益率以下の損失を相殺できるなど、投資資産全体として期待収益率からの乖離が小さくなることが期待できる。
長期投資の場合、ある時期に期待収益率以上の収益を得る場合とある時期に低収益や損失が出る場合とが相殺しあうことが期待でき、複利効果も期待できる。
さらに、長期期間にわたって毎月コツコツと定額投資を続けるなどの積立投資を活用して投資する時点を分散させると、価格が高い時に少ない投資単位を購入し、価格が低い時に多くの投資単位を購入することができるため、平均的な投資単価を低くし、収益率(=実現収益÷投資金額)を高めることも期待できる。
金融商品を選択するうえで考慮すべき個別条件
資産形成を行っていくうえで、選択するべき金融商品の期待収益率やリスクを検討することはもちろんである。
それに加えて、以下のような投資家の個別条件も考慮に入れるべきであり、投資家ごとに許容できるリスクの程度は異なる。
それゆえ、どの金融商品を選択するべきなのかという問題は、このような個別条件も含めて投資家ごとに決定されるリスク許容度に応じて投資家ごとに決定されるため、それぞれの投資家ごとにその答えは異なる。
○時間軸
将来のどの時点(例:結婚、進学、退職後など)において資金が必要になるのかによって、資産運用する期間が変わってくるため、リスク許容度は異なってくる。
一般的に、資産運用期間が短期であればあるほど投資に失敗した場合のリカバリーの可能性が小さくなるためリスク許容度が低下し、長期であればあるほどリカバリーの可能性が増えるためリスク許容度は高まる。
○余裕資金や収入、借入れなどの資産状況
一般に余裕資金が多いほど、リスク許容度が高まる。また、投資するのに一定規模の金額以上が必要な金融商品がある。
現時点で投資できる余裕金額の規模が大きいほど、投資可能な金融商品の数が増えることにつながり、分散効果も活用できるようになる。
また、余裕資金以外にも、給与水準や就業先の企業が提供している福利厚生の程度によっても投資家のリスク許容度は変わる。
たとえば、退職後の生活を十分にカバーするような退職金制度や年金制度があれば、投資家のリスク許容度は高まる。さらに、将来に住宅購入等の大きな出費が控えている、住宅ローン返済等、定期的に借入返済が必要であるなどの事情があれば、余裕資金の程度にもよるが、リスク許容度は低下することになる。
○税制
所得控除(保険料控除等、資産運用への投入資金に税金がかからない)の有無、非課税制度(NISA等、資産運用による利益に税金がかからない)の有無、損益通算(資産運用による損益の相殺)の可否など、投資家に適用される税制が金融商品ごとに異なる。
したがって、各個人の状況に応じて選択するべき金融商品の組合せ等も変わる。日本では、つみたてNISA等の非課税口座、個人型確定拠出年金(iDeCo)、保険商品等を活用することで税制メリットが得られる。
日本の年金制度
老後の生活資金の確保に向けた資産形成について考えるうえで、年金制度について知っておくことは重要である。
日本の年金制度は「3 階建て」と呼ばれる。企業(教員や公務員を含む、以下同じ)に勤める人は、20~60歳の全員が加入する国民年金(基礎年金)( 1 階部分)、企業に勤める人が加入する厚生年金( 2 階部分)、任意の企業年金など( 3 階部分)の3 つの年金制度と関連することになる。
⑴公的年金制度──国民年金と厚生年金
公的年金制度は、いま働いている現役世代が支払った保険料を高齢者などの年金給付に充てるという賦課方式で基本的に運営されている(保険料以外にも、年金積立金の運用収入や税金も充てられている)。
また、日本の公的年金制度は「国民皆保険」の特徴があり、20歳以上の人が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員(教員や公務員を含む)が加入する厚生年金などの2 階建ての構造になっている。
老後には、原則65歳(繰上げ受給や繰下げ受給の制度がある)からすべての加入者は老齢基礎年金、厚生年金に加入していた人はさらに老齢厚生年金が受給できる。年金の受給額は、老齢基礎年金は保険料を納めた期間に応じて、老齢厚生年金は保険料を納付した期間や賃金水準に応じて確定される。
日本年金機構によると、2020年度の年金額は、満額の場合の老齢基礎年金が約6.5万円、夫婦2 人分の老齢基礎年金を含む標準的な老齢厚生年金は約22万円となっている。
なお、年金の受給額は毎年度、2 つの観点で見直されている。1つ目は、賃金や物価が上昇した場合に年金の実質価値が変わらないように調整するものである。2つ目は、年金財政の健全性を維持するために少子化や長寿化の影響をふまえて調整するもの(「マクロ経済スライド」といわれる)である。
また、老齢基礎年金も厚生年金も基本的には65歳から受給が開始されるが、それぞれ1 カ月繰り下げるごとに0.7%年金額が増額される。したがって、5 年間繰り下げて70歳からの受給とすると年金額が42%増額されることとなる。ただし、制度が複雑で単純な損得計算はできないため、高度な知識が必要である。
老齢年金以外にも、病気やケガによって生活や仕事が制限される場合に現役世代も含めて受給できる障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)や、国民年金や厚生年金の被保険者がなくなった場合に生計を維持していた遺族が受給できる遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)がある。
○第1 号被保険者(自営業者、大学生など)
自営業者で国民年金に加入している人は、毎月定額の保険料を原則60歳まで自分で納める。国民年金の保険料は、物価変動率や実質賃金変動率などを加味して、毎年度見直しが行われている。
2020年度(2020年4 月~2021年3月)の第1 号被保険者(後述)および任意加入被保険者(国内に住む60歳以上65歳未満の人、国外に居住している20歳以上65歳未満の日本人などで、任意で国民年金に加入を希望する人)の1 カ月当りの保険料は所得にかかわらず一定であり、1 万6,540円となっている。
なお、まとめて前払いすると「国民年金前納割引制度」により割引が適用される。2020年度の老齢基礎年金受給額は、40年間加入していた場合、毎月約6.5万円である。
○第2 号被保険者(会社員や教員、公務員など)
厚生年金に加入している会社員(教員や公務員を含む)は、所得水準に応じて決定される毎月定率の保険料を企業と折半して負担する。
保険料は原則65歳まで毎月の給料から天引きされる。現在のところ、厚生年金の保険料は2017年より18.3%(会社と加入者の負担合計)で据え置かれている。なお、厚生年金の保険料には国民年金の保険料が含まれるため、会社員が自分で国民年金の保険料を納める必要はない。
夫婦2 人(夫が会社員で妻が専業主婦)で平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取る年金(老齢厚生年金と2 人分の老齢基礎年金)は、2020年度で毎月約22万円である。
○第3 号被保険者(主婦・主夫など)
第2 号被保険者に扶養されている人は第2 号被保険者が保険料を負担しているため、個人として保険料を負担する必要はない。
⑵国民年金基金制度
厚生年金に加入していない自営業者などの第1 号被保険者や任意加入被保険者が加入できる公的な年金制度で、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せして、老後の所得補償の役割を担う制度である。
自営業者等の2 階建て部分である。そのため、第2 号被保険者や第3 号被保険者は加入できない。また、第1 号被保険者であっても国民年金の保険料免除者、農業者年金の被保険者は加入できない。
⑶企業年金──確定給付年金と(企業型)確定拠出年金
企業が従業員の退職後の生活を支える福利厚生として企業年金と呼ばれる年金制度を提供していることがある。企業年金は、大きく「確定給付年金」と「(企業型)確定拠出年金」の2 つの種類に分かれる。
○確定給付年金(Defined Benefit:DB)
確定給付年金では企業が資産運用の責任を負い、従業員自らは資産運用をしない。転職すると、退職金として一時金を受け取れることもあるが、老後に年金として受給することはできない。
基本的に将来の退職金や年金給付額が約束されており、資産運用の状況が思わしくなくても企業より資金が補充される。
しかしながら、資産運用成績の悪化により企業の負担が重くなり過ぎると、企業業績が圧迫されて給与やその他の福利厚生に悪影響を及ぼすことがありうる。
最悪の事態として、企業が破綻した場合は年金減額などの影響を受けることがある。
○(企業型)確定拠出年金(Defined Contribution:DC)
確定拠出年金では、企業から一定の掛け金が支払われ、従業員自らが資産運用に責任をもつ。
確定給付年金とは異なり、原則60~70歳に一時金もしくは年金(10年間や15年間等の有期年金もしくは終身年金)、またはその組合せでの受取りを選択することができる。
ただし、各企業の制度ごとに選択できないものもあり、選択の幅には差がある点は注意が必要である。転職した場合は新たな勤務先などのDCや個人型確定拠出年金に加入する際の原資として活用できるが、転職時に退職金としては受け取ることはできない。
また、資産運用資金は信託銀行等で各個人ごとに分別管理されているため、企業が破綻しても影響を受けない。
⑷個人型確定拠出年金(individual-type Defined Contributionpension plan:iDeCo、イデコ)
個人で加入して老後に備える「個人型確定拠出年金(iDeCo)」と呼ばれる年金制度もある。企業が提供する確定拠出年金と同様に、加入している個人自らが資産運用に責任をもつ。個人で拠出する資金は所得控除され、資産運用による収益は非課税になるなどの税制メリットがある。
DCと同様に原則的に60歳までは受け取りはできず、70歳までに一時金や年金等での受取りを選択することができる。選択しない場合は70歳になった時に一時金で支払われることになる。
また、資産運用資金は信託銀行等で各個人ごとに分別管理されており、口座を保有している金融機関が破綻しても影響を受けない。
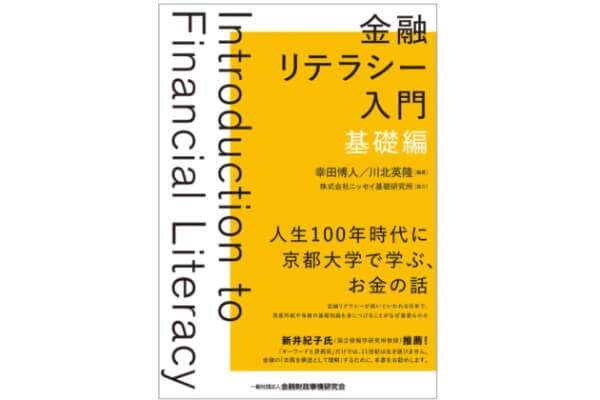
<編著者プロフィール>
幸田 博人(こうだ ひろと)
京都大学経営管理大学院特別教授・大学院経済学研究科特任教授 一橋大学経済学部卒。日本興業銀行入行、みずほ証券執行役員、常務執行役員、 代表取締役副社長等を歴任。
現在(2018年 7 月~)、株式会社イノベーション・インテリジェンス研究所代表 取締役社長、リーディング・スキル・テスト株式会社代表取締役社長、株式会 社産業革新投資機構(JIC)社外取締役、一橋大学大学院経営管理研究科客員教 授、SBI大学院大学経営管理研究科教授など。 著書に、『日本企業変革のためのコーポレートファイナンス講義』(編著、金融 財政事情研究会、2020年)、『プライベート・エクイティ投資の実践』(編著、中 央経済社、2020年)、『日本経済再生25年の計』(編著、日本経済新聞出版社、 2017年)、『金融が解る 世界の歴史』(共著、金融財政事情研究会、2020年)ほか。
川北 英隆(かわきた ひでたか)
京都大学名誉教授・同経営管理大学院特任教授 京都大学経済学部卒業、博士(経済学)。日本生命保険相互会社(資金証券部 長、取締役財務企画部長等)、中央大学国際会計研究科特任教授、同志社大学政 策学部教授、京都大学大学院経営管理研究部教授等を経て、現在に至る。 著書に、『株式・債券市場の実証的分析』(中央経済社、2008年)、『「市場」では なく「企業」を買う株式投資』(編著、金融財政事情研究会、2013年)ほか。



