『年収は「住むところ」で決まる 雇用とイノベーションの都市経済学』より一部抜粋
(本記事は、エンリコ・モレッティ(Enrico Moretti)氏の著書『年収は「住むところ」で決まる 雇用とイノベーションの都市経済学』=プレジデント社、2014年4月23日刊=の中から一部を抜粋・編集しています)
製造業の衰退は人々の生き方まで変えた
製造業は、もはや地域経済の繁栄のエンジンとは言えなくなった。かつて栄華を誇ったアメリカの製造業都市は往年の勢いを失い、人口の縮小と経済の不振に悩まされている。亡霊のように生気をなくし、経済の地図から完全に消滅しかねない瀬戸際に追い込まれた。
2000〜10年に人口が最も減ったアメリカの大都市圏は、2005年に大型ハリケーン「カトリーナ」で被災したルイジアナ州のニューオーリンズだが、そのあとに続くのは、ミシガン州デトロイト(25%減)、オハイオ州クリーブランド(17%減)、オハイオ州シンシナティ(10%減)、ペンシルベニア州ピッツバーグ(8%減)、オハイオ州トレド(8%減)、ミズーリ州セントルイス(8%減)といった工業都市だ。
アメリカの「ラストベルト(さびついた工業地帯)」の都市は、毎年毎年、巨大ハリケーンの直撃を受けているかのような惨状を呈しているのだ。デトロイトの人口は、1950年代後半に頂点に達し、それ以降は半世紀あまり減り続け、現在は100年前の水準まで縮小している。いまや居住者の三人に一人は、アメリカ国勢調査局の定める「貧困ライン」を下回る所得しか得ていない。暴力的犯罪の発生率は、毎年のように全米最悪レベルを記録している。工場や煙突や機械類が町を出ていき、それと一緒に製造業の良質な雇用と高給の職も町を出ていってしまったのだ。
ショッキングな数字だが、製造業の衰退が社会に及ぼす影響はこれだけにとどまらない。ある意味で、これまでの人々の生き方そのものが消失しつつあると言ってもいい。雇用論議では見落とされがちだが、製造業の衰退により地域社会がこうむる最も大きな打撃は、製造業で働いていた人たちが職を失うことではない。
工場が閉鎖されれば、その都市でサービス関連の仕事に就いていた人の多くも働き口を失う。私の研究によれば、製造業の雇用が一件減ると、最終的にはその土地で非製造業の雇用も一・六件減る。美容師やレストランのウェーター、大工、医師、清掃員、小売店の店員にも打撃が及ぶ。とりわけ影響が大きいのは、建設関連の雇用だ。
ラストベルト地帯では伝統的に、教育レベルの高くない人が就ける最も高給の職は、製造業以外では建設業の仕事だった。そうした建設関連の雇用は、大本をたどれば工場労働者が受け取る給料によって支えられていた。工場で働く人たちの収入が干上がれば、同じ都市に住むほかの人たちの収入も干上がるのである。
社会の雰囲気も暗くなっている。人々がアメリカの先行きに不安を感じていることは明らかだ。そうしたムードは、2008〜10年の景気後退をへて、今日まで続いている。
最近のある世論調査によると、製造業の衰退を理由に「経済的な不安」をいだいている人が多い。ボストン・グローブ紙の分析によれば、「アメリカが物づくりをやめてしまった」ことが不安の原因だという[1]。
ブルース・スプリングスティーンは1984年の曲「マイ・ホームタウン」で、工場の閉鎖により打撃を受けたアメリカ東部やラストベルト地帯の数知れない町を覆う不安感を表現した。
目抜き通りは、漆喰で閉ざされた窓と、主を失った店ばかり
もう誰もこの町に見向きもしないようだ
スプリングスティーンがこう歌って四半世紀あまり。歌詞に表現されている不安感はさらに広がっているようだと、ボストン・グローブは記事で結論づけている。
製造業の状況が暗転したことは、この60年間にアメリカ経済が経験したなかで有数の大きな変化だ。
もはやアメリカは、アメリカ人が自負してきたような「特別な国」ではない、という主張がなされるなど、アメリカの未来に対する悲観論が広がっている根底には製造業の衰退がある。アメリカの平均的な世帯の生活水準は1946年から78年にかけて二倍以上に上昇したが、それ以降はおおむね頭打ちになっている。
アメリカの平均的な勤労者――40歳の男性で、学歴は高校卒、仕事の経験は20年ほど――を考えてみよう。そういう人物の一時間当たりの賃金は、1946年から78年の間に8ドルから16ドルに上昇したが、今日は14ドルまで下がっている(金額はすべて今日の貨幣価値に換算)。
こうした事態を金融機関のせいだとする考え方は、2011年秋に一挙に盛り上がった「ウォール街オキュパイ(占拠)運動」が最初ではなく、昔から人々の心理に深く根を張っていた。
オリバー・ストーン監督の映画『ウォール街』(1987年)では、1980年代のアメリカ経済の変容を、誠実な市井の人々と倫理観の欠けたウォール街の戦いとして描いた。前者の象徴は、マーティン・シーン演じる実直な労働者。
いまの暮らしに満足していて、労働組合の活動に熱心に取り組んでいる。一方、後者の象徴は、その息子である若き証券マン。マーティンの実の息子であるチャーリー・シーンが演じた。この若者は、競争の激しい企業買収の世界で頭角をあらわすために手段を選ばず、しまいには父親が働いている会社を崩壊の寸前まで追いやるのだ。
アメリカの経済的苦悩に対するハリウッド流の解釈は、それから30年たっても変わっていない。2010年の映画『カンパニー・メン』では、ベン・アフレック演じるホワイトカラーの主人公が会社をクビになる。経営者がウォール街の顔色をうかがい、株価を引き上げるために、容赦ない人員整理に踏み切ったからだ。
2つの映画には、明確な共通点がある。いずれの映画でも、「善玉」は形のあるモノをつくっている会社の人たちで(マーティン・シーンの勤務先は航空機メーカー、ベン・アフレックの勤務先は造船会社)、「悪玉」は株式やら先物やらを売り買いし、売買の注文をひっきりなしに大声で怒鳴り、人々の雇用を破壊する連中だ。
『カンパニー・メン』に、こんな胸の痛くなるシーンがある。造船会社を解雇された二人の元社員が昔の仕事場を訪ねる。いまは使われなくなり、あちこちにサビが目立つようになった造船所だ。昔の職場で彼らは言う――「オレたちは、ここで物づくりをしていたんだよな」。
強欲な金融業者と、ビジネススーツに身を包んだ上昇志向の強い若きエリートたちは、物語の悪役としては打ってつけかもしれない。しかし、ブルーカラーのアメリカを本当に葬り去ったのは、ウォール街ではない。
本当の犯人は歴史だ。アメリカの製造業雇用が抱えている問題は、過去半世紀の歴史を通じて強まってきた根深い経済的要因を反映した、構造的なものなのだ。その経済的要因とは、グローバル化と技術の進歩である。
リーバイスの工場がアメリカから消えた日
アメリカの産業の歴史を象徴している会社を一つ挙げるとすれば、リーバイ・ストラウス(リーバイス)だろう。年代前半1990に私が移り住んだ当時、サンフランシスコにはまだリーバイスの工場が一つあった。
1853年、アメリカ西部がゴールドラッシュに沸いていたころ、24歳のドイツ系移民が金の採鉱者向けに頑丈なパンツを製造・販売しはじめた。こうしてリーバイスが誕生して以来ずっと、サンフランシスコの工場は操業を続けていた。
昔は、アメリカの都市近郊にこのような工場が無数にあったものだ。1994年夏に私がその工場を訪ねると、ラテンアメリカ系の女性を中心に何十人もの労働者が働いていて、看板商品である「リーバイス501」のジーンズをつくっていた。
そのとき脳裏に浮かんだ問いは、いまもはっきり覚えている――彼女たちの働き口は、いつまであるだろう? リーバイスはアメリカ国内の雇用を守ろうと努めていたが、一時間当たり九〜一四ドルの給料と付加給付を負担していた同社の製造コストは、ライバルに比べてかなり高かったのだ。
その後、2003年、同社はついにアメリカ国内の工場をすべて閉鎖し、生産拠点をアジアに移した。サンフランシスコの工場は、いまはクエーカー系の富裕層向け小学校になっている。学費は年間2万4045ドルだという。
工場閉鎖のニュースを聞いたとき、私は驚かなかった。むしろ、リーバイスがこれだけ長い間、アウトソーシングに抵抗し続けたことのほうが特筆すべきだ。同業のライバルであるギャップ、ラルフローレン、オールドネイビーなどは、もっと早い段階で国外での生産に転換していた。この面で、アパレル産業はアメリカ製造業の典型と言える。
第二次世界大戦後の10年間、繊維産業はアメリカの労働市場で重要な地位を占めていた。こと雇用に関して言えば、アメリカで最も貴重な産業集積地は、デトロイトの自動車産業ではなく、ニューヨークの衣料品産業だった[2]。
1980年代半ばのアメリカでは、まだ100万人を超す人たちがアメリカの衣料品メーカーで働いていた。いま、その数字は10分の1以下に減っている。あなたが着ている服は、どこでつくられたものだろう? もしアメリカ企業が販売している服を着ているとすれば、その服はおそらく、ベトナムやバングラデシュなどの業者が製造したものだ。アメリカのブランドは人気を博しているかもしれないが、アメリカ国内に残っている雇用は、デザイン、マーケティング、セールス関連など、ごくわずかにすぎない。
表面だけ見ると、iPhoneの物語と似た構図に思える。確かに、いずれの場合も、デザインとマーケティングの仕事だけアメリカに残り、製造はすべてアジアの業者がおこなっている。しかし、両者の間には大きな違いがある。アパレル産業の場合――これは従来型の製造業全般に言えることだが――アメリカにとどまるデザインとマーケティングの雇用は数が少なく、あまり増えていない。
それと対照的に、イノベーション産業では、デザインとマーケティング関連の雇用の数が多く、しかも雇用は急速に拡大している。
近年まで、アメリカは低所得国からさほど多くの輸入をしていたわけではない。
1991年の時点でも、こうした国々からの工業製品の輸入は全体 の3%に満たなかった。つまり、多くのアメリカ人の雇用に影響を及ぼすような数字ではなかったのである。しかしこの20年間、経済のグローバル化が進行し、貿易額が拡大し続けた。
アメリカの輸入先全体に占める低所得国の割合は、2000年までに二倍に増え、2007年までにさらに二倍に増えた。その増加分のほとんどを、中国が占めている。この時期、人件費の高い国から人件費の安い国へ、製造の場が移っていった。
iPhoneの物語からも明らかなように、製品をつくるうえでは、アメリカのような豊かな国よりもっと適した場所が地球上にはあるのだ。その点では、ある程度高度な製品も例外でない。
途上国は人件費が安いので、アメリカに比べて工場で人力に頼る傾向が強く、機械の使用が比較的少ない。その結果、途上国の工場は、状況の突然の変化に柔軟に対応しやすいという強みをもっている。「中国はコストが安いというイメージが強いが、本当の強みはスピードだ」と、中国でビジネスをおこなっているアメリカ人実業家は最近述べている[3]。中国で働くアメリカ人の工業デザイナーもこう指摘している。
「人間は、どんな機械よりも適応力がある。機械はプログラムし直さなくてはならないが、人間なら次の週にはまったく違う仕事をすることができる」。アメリカの工場と異なり、中国の工場は、それこそ一夜にして生産計画やデザインの変更をおこなえるのだ。
グローバル化がブルーカラーの雇用に及ぼしている影響は、地域によって異なる。デヴィッド・オーター、デヴィッド・ドーン、ゴードン・ハンソンの最近の研究によると、中国からの輸入によって地域の雇用がどの程度影響を受けているかは、土地によって大きな違いがある[4]。
プロビデンス(ロードアイランド州)やバッファロー(ニューヨーク州)は、伝統的な製造業への依存度が高く、中国でも製造しているような付加価値の低い製品を主につくっている。これらの地域は、競争が激化したことで大きな打撃をこうむった。
対照的に、ワシントンDCやヒューストン(テキサス州)はまったく異なるタイプの製品をつくっており、打撃は比較的小さい。中国と直接の競争関係にある都市では、輸入が増えるにともない、失業率が上昇し、労働参加率が低下し、賃金が下落している。
注目すべきなのは、ツケを払わされるのが職を失う労働者だけではないということだ。アメリカ国民全体にしわ寄せがいく。失業して困窮した人たちに、さまざまな形で政府から金が流れるからだ。失業保険やフードスタンプ(低所得者向けの食料費補助制度)、さらには障害保険などの福祉給付が増大するのである(障害保険は、形を変えた低所得者向け福祉制度として利用されていることが多い)。
要するに、貿易の直接的な影響に関しては地域ごとの違いがきわめて大きいが、それが生み出すコストの少なくとも一部は、最終的には納税者全体が負担することになるのだ。
企業がグローバル化の影響をどのように受けるかは、個々の企業の対応能力次第で大きく変わってくる。
ニコラス・ブルーム、ミルコ・ドラカ、ジョン・ファンリーネンの最近の研究によれば、途上国との貿易が増えると、全般的に企業の技術向上のペースが加速するが、個別の企業に及ぶ影響は、その会社にどのくらい適応への意欲があるかによって決まる[5]。
ブルームらが先進12カ国の50万社について1996〜2007年のデータを調べたところ、中国からの輸入品との競争にさらされている企業は概して、自社の技術を向上させることで対応しようとしていた。コンピュータを新たに購入したり、研究開発への投資を増やしたり、特許を積極的に取得したり、経営方針を刷新したりする。
皮肉なことに、外国からの脅威がアメリカ企業の生産性向上を誘発し、アメリカの経済成長を後押ししているのである。しかし、誰もがその恩恵を受けるわけではない。ハイテク企業が脅威にうまく対処する一方で、ローテク企業――イノベーション性に乏しく、ITにあまり投資せず、生産性も高くない企業――は、中国の輸出攻勢の前に苦戦を強いられ、従業員を解雇したり、市場から撤退したりしている
要するに、グローバル化は技術の進歩を促し、教育レベルの高い働き手に対する需要を増やすが、技能の乏しい働き手への需要は減らしてしまうのである。
[1] Jacoby, “Made in the USA.”[2] Glaeser, Triumph of the City.
[3] Fallows,“ China Makes, the World Takes.”
[4] Autor, Dorn, and Hanson,“ e China Syndrome.”
[5] Bloom, Draca, and Van Reenen,“ Trade Induced Technical Change?”
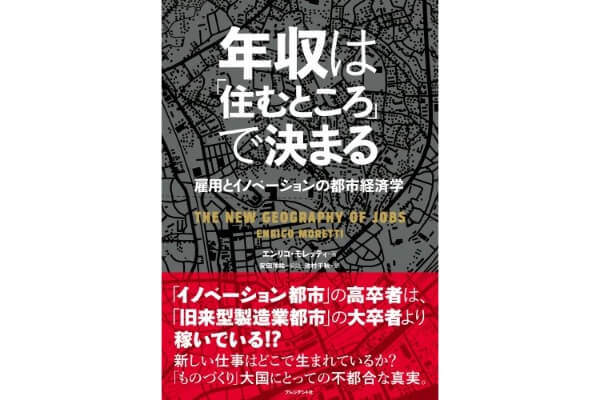
エンリコ・モレッティ(Enrico Moretti)
経済学者。カリフォルニア大学バークレー校教授。専門は労働経済学、都市経済学、地域経済学。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)国際成長センター・都市化プログラムディレクター。サンフランシスコ連邦準備銀行客員研究員、全米経済研究所(NBER)リサーチ・アソシエイト、ロンドンの経済政策研究センター(CEPR)及びボンの労働経済学研究所(IZA)リサーチ・フェローを務める。イタリア生まれ。ボッコーニ大学(ミラノ)卒業。カリフォルニア大学バークレー校でPh.D.取得。
『年収は「住むところ」で決まる 雇用とイノベーションの都市経済学』



