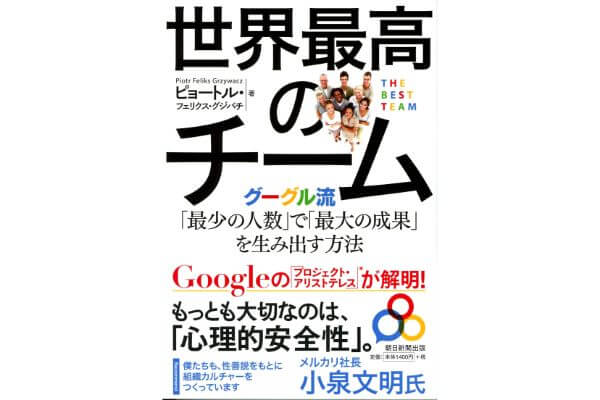『世界最高のチーム Google流「最少の人数」で「最大の成果」を生み出す方法 』より一部抜粋
(本記事は、ピョートル・フェリクス・グジバチ の著書『世界最高のチーム Google流「最少の人数」で「最大の成果」を生み出す方法 』=朝日新聞出版社、2018年08月20日刊=の中から一部を抜粋・編集しています)
目次
「報・連・相」はやりすぎぐらいでちょうどいい
じつは、僕(筆者)がGoogleに入って一番驚いたのは「オーバーコミュニケーションが大切にされている」ということでした。
アンダーコミュニケーションというのは「報(報告)・連(連絡)・相(相談)」が足りない状態、オーバーコミュニケーションというのは「報・連・相」をやり過ぎている状態のことです。
Googleのマネジャーには、毎日たくさんのメールが入ってきます。個人個人のスニペット(その日その日の成果や申し送りを短く簡易的にメモしたもの)、プロダクトのアップデート、ピアボーナス─あらゆることが情報共有される仕組みになっています。
その量の多さには、きっとだれもがびっくりすることでしょう。僕も最初のうちは大量のメールを見て、「これ、全部やらなきゃならないの!」と頭を抱えてしまいました。
もちろんそうではなくて、その情報が自分に必要かどうかを自分で判断して自発的に動くということが求められているわけです。
要するに情報共有されるメールというのは、「これをやってください」というような、いわば仕事の依頼ではなくて、ほとんどが「これがあるので必要なら動いてください」というような、いわば報告なのです。
マネジャーはチームのエバンジェリストであれ
とはいえ、なぜオーバーコミュニケーションが仕組み化されているのか。
当時のGoogleではみんな自分がどれくらい仕事しているのかどんどん報告します。そのために、報告しない人はその存在が忘れられてしまいかねません。だから、みんなどんどん報告するわけです。
当然ながらチームのマネジャーにもオーバーコミュニケーションが求められます。「うちのチームは今週、これやりました」とか「今日あったすごくいい事例です」とか「Aさんは頑張ってくれました」といった報告を、みんなにいちいちシェアしておかないと、「あいつら、何もしていない」と思われてしまいかねないのです。
それができないマネジャーはまったく評価されません。僕も慣れるまでは、上司に自分のチームのスニペットを報告し忘れてよく怒られました。つまりGoogleには、「マネジャーはチームのエバンジェリスト(伝道者)でなければならない」という文化があるわけです。
なぜそのような文化が根付いたかと言えば、個人やチームのブランディングにかかわるからでしょう。
せっかくいい仕事をしていても、そのことがシェアされていないとだれにもわかりません。シェアされていれば、20%ルールを使って「かっこいいね、自分も手伝いたい」という人がどんどん集まってきて、より大きなインパクトのアウトプットを生み出す可能性が出てきます。
その中心に自分や自分のチームがいるということは、当然ながらブランディングに直結します。だから、みんな頑張って自分やチームの仕事ぶりをアピールするわけです。
つまり、ブランディングを妨げるシェアしかできないマネジャーには大きな成果が期待できないということ─。評価が下がって当然ですね。
ちなみに20%ルールには、「いまと違う職場で自分のスキルを高めて、違う仕事もできるようにする」という、いわばトレーニングの機能もあります。
Googleではみんなよく異動します。組織改編が多いので仕事内容も変わりやすく、次のチームに行くか、違う仕事をするかといった選択を迫られることがたびたびあるのです。その際は、もちろん自分で決めないといけません。
つまり、こうした組織改編にともなう選択の幅を広げることにも、20%ルールは一役買っているわけです。
マネジャーはチームメンバーのアウトプットで評価される
当たり前の話ですが、実際に大きなインパクトのアウトプットがないと、みんなに報告したくても報告できません。
ただマネジャーの役割は、自分自身がアウトプットを出すことではなくて、あくまでもメンバーのアウトプットを最大限に引き出すために「判断する」ことです。なので僕はGoogle時代、自分のチームのメンバーには「手ぶらで〈どうしたらいいですか?〉と聞かないでください」とお願いしていました。
「これか、これか、これか、どれがいいか教えてください」とか「こうつくったので見てください。ポイントはこれです」といった、たたき台がないと、マネジャーとしては判断できないし、メンバーやチームのブランディングに役立つようなアピールができないわけです。
こうした「コミュニケーションのルール」もチームに必要な仕組みの一つと言えるでしょうね。
他のチームとの接点を増やせば、「思いがけない発見」も増える
当時のGoogleでは、セレンディピティ(思わぬものを偶然に発見すること)にかかわる仕組みも印象的でした。
簡単に言うと、Googleという会社の文化とは「すごいことを自発的にやる」ということです。みんながいつも「すごいことって、なんだろう? どこにある?」と考えていて、探し求めています。
なので、自分の仕事の領域や役割を超えた人たちとできるだけ接すること、つまりセレンディピティが重視されるわけです。自分が所属する縦割りの範囲内や自分と同じレベルの人とつき合っていても「思いもよらない、すごいもの」を見つける可能性は、ほとんどゼロですからね。
その意味では、社長に直接質問できる毎週金曜の全体ミーティング「TGIF」もセレンディピティにつながる仕組みと言えます。
また、オフィスのレイアウトがセレンディピティを促すような仕組みになっています。たとえば、チームごとにデスクの配置を好きなようにアレンジできるというのもその一つでしょう。
顔を合わせて仕事をしたほうがいいのなら向かい合わせ、一人ひとり集中したほうがよければ放射線状に背中合わせにする。立ちながら作業できるスペースを設けたり、一人になれる個室ブースをつくったり、ど真ん中にみんなでブレストできるテーブルを置いたりと、チームによっていろいろな違いが出てきます。
要は、チームの数だけ「コミュニティ」があるというような雰囲気ですね。つまり、他のチームをのぞくだけでも「思いがけない発見」が期待できるわけです。
そして、フロアのセンターには「マイクロキッチン」が設置されていました。お菓子や飲み物が置いてあって、みんなそこに取りに行くわけですが、面白いのは、キッチンに出入りする通路がかなり狭くなっていること─。
なぜ、わざと狭くしたのか。じつは、人がすれ違うときにぶつかりやすくするためなのです。ぶつかったら、そこで「思いがけない会話」が交わされます。その偶然の出会いが、何かすごいものを生み出すきっかけになるかもしれません。もちろん恋が芽生えても、それはそれですごいことでしょう。
マイクロキッチンの狭い出入口は、Googleのセレンディピティ文化をわかりやすく表現していると思います。
いまの自分の仕事をなくしていくのが、マネジャーの仕事
なんのために人・テクノロジー・プロセスを仕組み化するのか。簡単に言えば、自分がここにいなくても仕事が回るようにするためです。つまり、いまの自分の仕事をなくして違う仕事をするためなのです。
その意味でも、日本式のプレイング・マネジャーは、どんどん部下に自分の仕事を任せていくべきだと思います。そして、いまの自分よりも上のレベルの仕事をどんどん増やすように心がけてほしいのです。
もし「面倒くさい」とか「つまらない」と感じているなら、なおさらでしょう。自分がやるのではなく、違う人にやってもらったほうが建設的ですね。自分は違う職場に異動したらいいだけのことです。
戦うフィールドは社外にも広がっている
ただ、残念ながらこうした働き方ができない会社も少なくないでしょう。日本には真っ当な「組織開発」ができていない会社がいまだに多いようですから(先の章で紹介した「オールドエリート」の例で十分でしょう)。
それでもチームの代表者として、ぜひ上司たちと戦って一歩ずつでも実現していってほしいと思います。
先の章で「経営判断の核心はインパクトと成長」と述べました。それを第一に考えている上司たちなら、「自分のチームをこうしたい」「自分の働き方はこうしたい」とプライドを持って説得していれば、必ず通じるはずです。もし戦って戦って、どうしても上司たちの判断が変わらないときには、会社を辞めたらいいだけのことです。
決して恐れることはありません。自分が持っているスキルやポテンシャルを十分に発揮できる環境は、いまや世界中どこにでもあるのですから。社会主義だったポーランドの田舎の村で生まれ育った僕が大丈夫だったのですから、日本のビジネスパーソンにできないはずがありませんね。
『世界最高のチーム Google流「最少の人数」で「最大の成果」を生み出す方法』