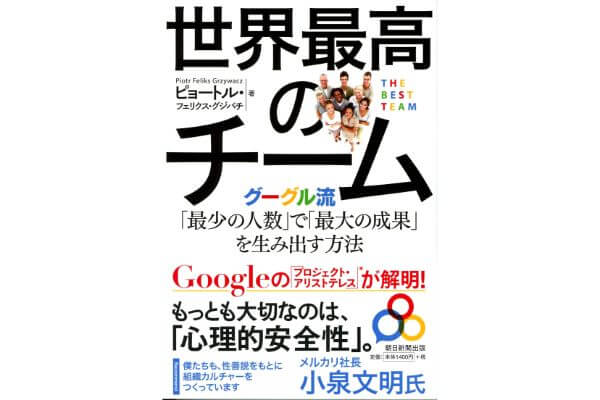『世界最高のチーム Google流「最少の人数」で「最大の成果」を生み出す方法 』より一部抜粋
(本記事は、ピョートル・フェリクス・グジバチ の著書『世界最高のチーム Google流「最少の人数」で「最大の成果」を生み出す方法 』=朝日新聞出版社、2018年08月20日刊=の中から一部を抜粋・編集しています)
目次
タイプの異なる3人のチームメンバーを組み合わせる
「ディズニー・ストラテジー」という有名な「戦略」があります。ウォルト・ディズニーは映画を制作するとき、アイデアから実現に至るプロセスの中で相談するメンバーを必要に応じて変えていたといいます。
一番初めはドリーマー(夢想家)たちとのブレスト。我々は何をするべきか、なんの制限も考えずにアイデアを出し合う。「まず大きい話、夢の話をしよう」ということです。
アイデアが固まったら、次はリアリスト(現実主義者)たちと話し合う。いかにそれを実現するか。いまどんなことができるか。実現可能な事柄をあげて、「こういう動きでやってみよう」と具体的なプランをつくります。
そして最後に、クリティック(批評家)たちに「こういうプランをつくったんだけど、どうかな?」と相談する。どんなリスクがあるのか。どんなネガティブな影響があって、どこから抵抗がありそうなのか。ネガティブな要素を建設的に洗い出すことで、まずはこれ、次はこれと、本当にアイデアを実現させるためのプロセスが完成するのです。
要するに、チームミーティングでは話し合うテーマによって、ドリーマー的な人が活躍するときもあれば、リアリスト的な人やクリティック的な人が貢献するときもあるわけです。
メンバーのマインドセットの多様性が、チームの集合知を高めてくれる
僕(筆者)のチームも少人数とはいえ、ドリーマー、リアリスト、クリティックのバランスを意識した構成になっています。
たとえば、Googleにならい「OKR」(223ページで詳述)の共有システムを導入しようとチームミーティングを行ったときのこと。当時のGoogleでは、社員みんながそれぞれのOKRを登録していて、その進捗状態をトラッキング(追跡、追尾)できるシステムになっています。
それを提案した僕は、いわばドリーマーですね。一方、アシスタントの女性はクリティック。いつも「そもそも間違っているんじゃない?」「面倒くさいね」などと、いい意味で慎重な指摘をしてくれます。
もう一人の若い女性スタッフはリアリスト。なので、僕は彼女に確かめるわけです。「どう思いますか? 面倒くさいですか?」「ああ、いいと思います。みんなでまず使ってみて面倒くさければ違うシステムにすればいいんじゃないですか?」というような、現実的な答えが返ってくるわけです。
そうすると、否定的だったアシスタントの女性も「じゃあ、試してみようか」となって、「ただ、こういうところが心配」といった単なる批評にとどまらない、アイデアの実現に向けた建設的な意見を言ってくれるようになるのです。こうしたメンバーのマインドセットの多様性も、チームの集合知を高めるためには大事だと思いますね。
異なる個性を組み合わせるにはルールが必要
加えて、建設的な議論のためには、マネジャーによるファシリテーションが非常に大事になってきます。状況に応じて、メンバーそれぞれの個性を建設的に使えるかどうか。それは、ファシリテーターであるマネジャーの力量次第と言えます。
たとえば、よくありがちなのは、アイデア出しのブレストであるにもかかわらず、「これ、うまくいかないんじゃないの?」などと、クリティック的なメンバーが批判し始めるというパターン─。
なぜ、求められていない行動を取る人が出てくるのか。それはマネジャーがファシリテーションしていないからですね。「アイデアを出す時間ですよ」ということをしっかり前置きすれば、こうした非生産的な批判は出てこないはずなのです。
「いまから、みんなでアイデアを出し合って、一番いいアイデアを選びましょう。だから批判するんじゃなくて、とにかくいろんなアイデアを出してください」などと、初めにその場の「ルール」を明確に伝えておく。そうすれば「ああ、そうか、いまは批判する時間じゃなくて、アイデア出しの時間なんだな」とメンバー全員が共通の認識を持つわけです。
それでも、そもそも論的な批判が出てきたらどうするのか。感情的になって制止してしまったら逆効果でしょう。「わかりました。賛成できないんだったら、あとで時間をつくるのでそのときに話してください。だから、いまはポジティブなアイデアを考えてみてください」
こんなふうに、穏やかな口調でお願いすればよいのです。そして日を改めて、そもそも論的なテーマについて話すチームミーティングの機会をつくって、約束を果たすこと。マネジャーがメンバーに信頼されるためには、こうしたフォローも大事ですね。
チームの日常業務もする「プレイング・マネジャー」になってはいけない
自分のチームでマネジャーとしての役割を果たすことは当然として、マネジャー自身も、上のマネジメントチームでメンバーとして果たすべき役割があります。そのレベルでの仕事こそがマネジャー自身の仕事と言えるわけです。
よく日本では「プレイング・マネジャー」という言い方をしますね。当時のGoogleでもほとんどのマネジャーはプレイング・マネジャーなのですが、日本のそれとは意味合いが違います。日本の会社のように自分のチームの日常の業務をやるというのは、ほとんどありません。
Googleでは、たとえば5人の部下がいるマネジャーの同僚というのは、隣のチームの5人の部下がいるマネジャーです。つまり、同じファンクション(役割、職務)で違うロケーション(場所)のマネジャー。そのマネジャー5人がメンバーになって、一つのチームとして動いていくわけです。
そうした構造はトップまで同じです。要するに、個人主義に徹しているように見えるGoogleでも「一匹オオカミ」はありえません。一匹オオカミ的に働く人の評価は極めて低いのです。
つまり、同じレベルのマネジャー同士が仲よくして、チームとしてのコンセンサス(合意)を取って、一緒にアウトプットを生み出すわけです。当然ながら、マネジャー自身のOKRや「20%ルール」(Googleでは、自分の仕事以外のプロジェクトにも契約時間の20%以内なら自由に参加することができます)などもこのレベルで行います。
ちなみに、マネジャー自身の心理的安全性は、その上のチームマネジャーによって醸成されるのです。
正しい「プレイング・マネジャー」とは
僕は日本式のプレイング・マネジャーについて、かなり問題だと感じています。日本でプレイング・マネジャーと呼ばれているのは、「自分もチームのメンバーと同じ業務をやりながらチーム全体の面倒も見ているビジネスパーソン」のことでしょう。
また、そういう働き方をしているチームマネジャーがほとんどなので、マネジャーの仕事とはそういうもので、「とにかく忙しいのがプレイング・マネジャー」というイメージが強いと思います。
Googleのチームマネジャーも、もちろんプレイング・マネジャーです。そして日本の会社のマネジャーに負けないくらい忙しい。ただ決定的に違うのは、「チームのメンバーと同じ業務はしていない」という点です。繰り返しになりますが、プレイングするのは、あくまでも係長なら係長レベル、課長なら課長レベルのチーム内において、なのです。
そのマネジャーチームのために議事録を取ったり、企画書をつくったりといった業務をやりますが、自分のチームに関しては、まさにこの本で説明している「マネジメント」に徹しているわけです。
問題は、同じように忙しいならどちらの働き方のほうがより生産性を向上させるのか、ビジネスパーソンのスキルやキャリアを高めるのか、ということでしょう。その意味で僕は、自分も隣の部下と同じような日常業務をこなしているような日本のプレイング・マネジャーの働き方は、大きく間違っていると思うのです。
「ポートフォリオ・マネジャー」になろう
日本式のプレイング・マネジャーの最大の問題点は、そうした形態や意識では、いまと同じような仕事の進め方しかできず、ほとんど生産性を上げることが期待できないということです。
どんなチームのミッションでも、突き詰めると「どんな価値を生み出すか」ということになりますね。そして繰り返し述べているように、その価値をいかに短時間で、いかに安く、いかに大きくアウトプットするかということを考えるのがマネジャーの大事な役割です。
先の章で、「これからのマネジャーは、社内・社外のあらゆるリソースを活用してポートフォリオ(最適な組み合わせ)をつくることが求められている」と述べました。
つまり、全部のプロセスを考え直して、大胆に業務を委託したりテクノロジーを使ったりできる「ポートフォリオ・マネジャー」でなければ、生産性を大きく向上させることはできないのです。
「この仕事には、やっぱり部下が5人いないとダメですね」などと思考停止になっているのが日本式のプレイング・マネジャーでしょう。そうではなくて、「コンサルを入れましょう」とか「派遣社員を入れましょう」とか「クラウドソーシングでやってみましょう」というふうに、人材やテクノロジー、プロセスをいかに最適化するかを常に考え続ける─。それがポートフォリオ・マネジャーなのです。
日本式のプレイング・マネジャーにありがちなのは、「メンバー5人のチームだったら5人を使わないといけない」と思い込んでいることです。けれどもよく見れば、なんの価値も生み出していない人がいて、その人にとってもこのチームにいる時間に意味がない。となると別のチームに異動してもらって、そこで貢献してもらうほうがいいわけですね。
また、テクノロジーを取り入れるなどして、プロセスを改善したなら、5人ではなく3人でできる仕事なのかもしれません。チームを小さくすることでコストが下がるし、会社全体としても、メンバーの異動によってより有効に人材を活用することができるのですから、生産性の向上につながるわけです。
また、業務委託やテクノロジーの導入によって、時間に余裕ができたメンバーはより価値の高い仕事に注力できるようになるはずですね。
部下を育てるからこそ、別の仕事に挑める
僕がGoogleにいた当時アジア・パシフィックの人材育成を統括していたので、その地域の代表としてグローバルチームに入っていました。僕の同僚はヨーロッパとアメリカの人材育成の統括者たちです。
つまり僕は、グローバルチームの人材育成のトップがマネジャーを務めるチームのメンバーの一人としてプレイするプレイング・マネジャーだったわけです。
たとえば、僕が自分の仕事として頑張っていたのは全世界の人材育成の戦略をつくることでした。アジアのトップとして自分の部下とディスカッションしてアジアの戦略をつくり、ヨーロッパのトップとアメリカのトップと3人で擦り合わせて世界戦略をつくる。ほかにも人材配置や給料・ボーナスの分け方など、自分の部下には任せられない仕事がたくさんあったわけです。
ただ裏返して言うと、アジア・パシフィックの中では部下に任せられる仕事はどんどん任せていたということなのです。そうしないと、本来やるべきグローバルチームでの仕事ができなくなって、生産性を高めることができないから。また、仕事を任された部下のスキルやキャリアは当然ながら向上していくわけです。
ひるがえって日本のプレイング・マネジャーはどうでしょうか。自分の部下と同じレベルで業務をこなしている限り、会社全体の生産性を向上させることはできないし、優秀な部下、つまり「次のマネジャー」も育たないのではないでしょうか。
チームメンバーをアシスタントのように使ってはいけない
「ビジネスチームはスポーツチーム」と何度か述べました。その比喩を使えば、日本式のプレイング・マネジャーは、サッカーの試合中に監督が選手と一緒に走ってボールを蹴っているようなものなのです。本来的にはそれはありえない─。
監督の仕事は、試合のときにはピッチの外から見て、「こうしよう、ああしよう」と指示することです。練習のときには選手がもっとかっこよくボールを蹴れるようにサポートする。チームが勝てるように戦術や選手同士のいい関係性をつくっていく。当たり前のことですが、選手と監督では仕事の内容がまったく違いますね。
要するに、チームのマネジャーというのは現場の仕事をする役割の人ではないのです。ところが日本の会社では、チームのメンバーをアシスタントのように使って、マネジャーが現場の仕事をやり続けています。
『世界最高のチーム Google流「最少の人数」で「最大の成果」を生み出す方法』
[/box]