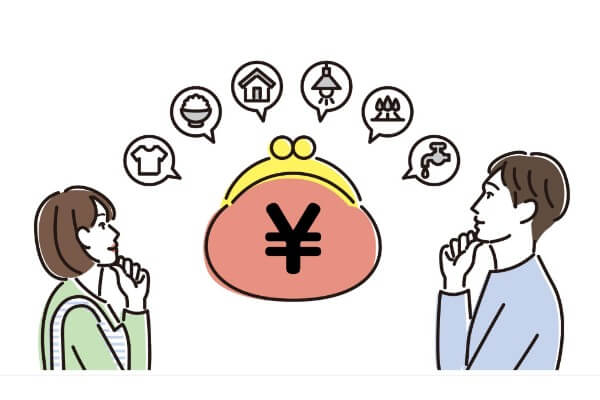『教養としての金融危機』より一部抜粋
(本記事は、宮崎 成人氏の著書『教養としての金融危機』=講談社 、2022年1月19日刊=の中から一部を抜粋・編集しています)
危機の残したもの
ユーロ危機の源泉は、通貨統合のイメージが先行して、南欧諸国で財政状況からは正当化されない金利の急速な下落が起こり、それによって生じた好況と住宅バブルが崩壊したことです(55)。しかし、そもそもその状況は、政治主導で通貨統合を性急に進めたことによって作り出されたのでした。単一通貨に至る統合の道はとても美しいですが、統一のための経済的条件は整っているか、各国の国民レベルで通貨統合のもたらすプラスとマイナスについて政治的な合意ができているか、仮に統合がうまくいかなかったときの「逃げ道」は用意されているか、といったあたりの詰めが甘かったのではないでしょうか。
通貨統合を具体的に検討している国は欧州以外では極めて少数ですから、ほとんどの国にとって、ユーロ危機の経験から学ぶ教訓はないと言って良いでしょうか?
それは、やはり違うでしょう。もし学ぶことがないと言っては、数年間にわたり必死に危機を回避・解決しようと努力した国際社会と、不況に苦しんだ危機国の国民に失礼だと思います。では、我々はユーロ危機から何を学んだでしょうか?
(1)政治的理念は極めて重要ですが、やはり情熱が先に立っては危険な場合があると思います。EUのガバナンスについては、EU本部(ブリュッセル)の官僚組織が理詰めで考えた計画を、各国首脳が政治的バーター取引で決めていって、民意が反映されていない、という批判がしばしば寄せられています。これは、通貨統合に民衆の同意がなかったということではありません。ユーロが現在でも高い人気を得ているのは事実です。しかし、マーストリヒトクライテリアの遵守が参加条件だったのに、いつの間にか特例措置を乱発して南欧諸国のユーロ参加を許してしまうように、政治的便宜で経済的合理性が捻じ曲げられたことが、ユーロの危機につながり、ひいては政治的リーダーとブリュッセルへの信頼低下につながっていると思います。リーダーには先に立って世の中を引っ張るイメージがありますが、謙虚に庶民と歩みを合わせるのも、「急がば回れ」の危機回避かもしれません。
(2)ユーロ圏は日本や米国に比べると、はるかに財政規律を重視します。危機国への財政支援は加盟国全体のコンセンサスが必要ですが、ドイツやオランダ、北欧等の財政規律を極めて重視する北部諸国では、南欧諸国やアイルランドは規律に欠けた経済運営を行っていたのだから危機になったのは自業自得だという、倫理的な見方が広がっていました。ドイツ語で「債務」を表わす「Schuld」という単語には、「罪」という意味もあるほど、ドイツ語圏では債務を忌避する感覚が強いそうです。財政に対する考え方が全く異なる二つのグループがユーロ圏内に存在するので、危機国への支援を機動的に行うのは困難でした。
こうした意見の相違はユーロ圏に限りません。市場と政府の役割、社会保障のあり方、格差への対応、規律と成長の優先順位、金融規制の強弱、財政赤字への抵抗感等のテーマへの考え方は国内でも往々にして意見が分かれていますから、まして国と国との間では様々です。いかに米国が世界最大の経済大国とはいえ、米国の考え方が常に勝つわけではありませんし、米国の考え方も政権や時代によって移り変わります。そもそも、各国の意見が一致する方が珍しい、という中で危機対応を行うのは簡単ではないのです。
(3)米国や日本でも同様ですが、銀行への公的資金による資本注入に対しては、バブルに乗って調子よく儲けていた銀行を、一般大衆が苦労して支払う税金で救うのか、という極めて大きな反発に直面します。加えて、失敗したときに公的資金で救われるのであれば、次回以降も高リスクのギャンブルを促しかねないというモラルハザードへの心配も、もっともなことです。
しかし、金融システムに影響が及ぶような重要な銀行が傾いたら、批判を乗り越えて資本注入や国有化を行わざるを得ません。救済しないコストがあまりに大きいからです。もっとも救済の財政コストも大きいのが悩ましいところです。財政の持続可能性と銀行の健全性が一蓮托生となってしまうと、銀行を支援すればするほど国家の信用力が下がることになります。国民生活は、いずれにせよ大きな打撃を受けるでしょう。
(4)ユーロ圏では、一国の危機が単一通貨の信認を直撃しますので、他の参加国が(仮に渋々であっても)公的資金を用いて危機国を支援しました。より一般的に考えても、単一通貨であるか否かにかかわらず、危機国に近接する地域の友好国が支援を行うのが自然のように思われます。危機の伝播の可能性を考えると、隣国の危機を早期に収束できれば、自国の利益にもかないます。
アジアでチェンマイイニシアティブが作られたように、ユーロ圏でも危機の最中に作られた組織を統合して、2012年10月に「欧州安定メカニズム」(ESM)が設立されました(56)。アジアと欧州のモデルにならって、今後同様のメカニズムが他の地域でも作られていくのではないでしょうか。
(5)ユーロは崩壊を免れましたが、ユーロ参加国が経済的にも政治的にも文化的にも一枚岩でないことが誰の目にも明らかとなりました。メンバー間の経済力格差は継続し、ギリシャ等は今後数十年にわたって緊縮政策を行って、支援を受けた国々に債務を返済することが義務付けられています。しかも、「危機が起こらないように平時から財政規律を維持しておくべきだ」という考えと「危機の原因は問わず、危機の際にはユーロ圏全体の利益を考えてすべての国の負担で危機国を支援すべきだ」とする考え方の間の溝は依然として埋まっていないのが実態です。仮に再度危機が発生したら、インターナル・デヴァリュエーションがもう一度強制されるでしょう。こうして考えると、ユーロは当分の間、脆弱な巨人であり続け、ドルに代わる基軸通貨への道のりは遠いものと思われます。
ユーロ危機は、先進国でもサドンストップに直面し得ること、硬直的な為替制度は問題を悪化させること、肥大化した金融セクターはそれ自体が大きなリスクとなること、投資家の信認が危機解決のカギであり、そのためには当局の肝の据わった対応が不可欠なこと等を改めて示しました。
さらに言えば、危機になってからそれを解決するのでなく、危機を未然に防ぐことの方が、はるかに重要であることも再確認しました。残念ながら、未然に防いだ危機は国民の目には見えません。危機予防のため、事前に財政・金融政策を引き締めたり、規制を強化したりすることは、おそらく不人気でしょう。
2000年代前半にはドイツに匹敵する生活水準(一人当たり実質GDP)であったイタリアは、その後生活水準が1割以上下落し、現在でもユーロ危機以前の水準を回復できていません。また、長期にわたって緊縮財政の継続が求められているギリシャの生活水準は、2000年代半ばのピークから2割以上低下し、その後も独仏との差が開くばかりです。こうした数字を見ることで、ユーロ圏のみならず世界中の国が、平時から危機予防を真剣に考えるようになったと信じたいところです。
(55)アイルランドの金利も1990年代後半に下落しますが、アイルランドは財政の黒字化に成功していたので、金利低下が全く正当化されないというわけではありません。
(56)ESMは市中借入れを基に危機国に融資を行い、財政移転は行いません。
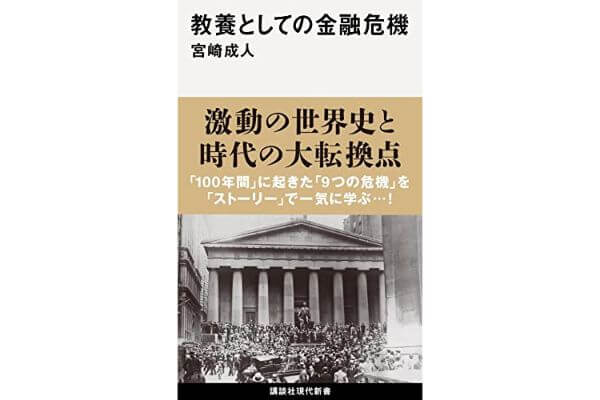
<著者プロフィール>
宮崎 成人
1962年東京都生まれ。1984年東京大学法学部卒業。1988年英オックスフォード大学にて国際関係論修士号(M.Phil)取得。1984年大蔵省(現・財務省)入省。主計官、国際機構課長、副財務官など歴任。欧州復興開発銀行(EBRD)日本理事室、金融安定化フォーラム(FSF)事務局での勤務を経て、2008~2016年国際通貨基金(IMF)アジア太平洋局及び戦略・政策・審査局審議役、2017~2021年世界銀行駐日特別代表。ロンドン、バーゼル、ワシントンなどで通算17年間海外勤務。2016年より、東京大学大学院(総合文化研究)客員教授。現在、三井住友信託銀行顧問。