『教養としての金融危機』より一部抜粋
(本記事は、宮崎 成人氏の著書『教養としての金融危機』=講談社 、2022年1月19日刊=の中から一部を抜粋・編集しています)
第3の危機 なぜドルは大暴落したのか?ーー変動相場制、オイルショック、インフレ
なぜ米国はドル安に直面したのか
米国に対するイメージは、世代によって様々だと思います。第二次世界大戦直後の世代は、米国の圧倒的なパワーと豊かさに対する憧憬の念を覚えたでしょうし、現在の若者はGAFAに代表される最先端技術やスタートアップのダイナミズムに心震える思いを持つでしょう。他方で、地球温暖化問題への取り組みや国内人種問題への対応等に幻滅する人々も少なくありません。
1970年代の米国は、同時代の人々にはどのように映っていたでしょうか?
文化的な発信力は依然として強力でした。何しろ、「スター・ウォーズ」が封切られ、イーグルスが「ホテル・カリフォルニア」を歌っていたのですから。しかし、政治・経済的には、底の見えない深みにはまっていくような、閉塞感漂う時期でした。
政治面では、ウォーターゲート事件によるニクソン大統領の辞任(1974年)、南ベトナムの崩壊を受けたサイゴン(現ホーチミン)からの不名誉な撤退(1975年)、イラン革命の際の大使館占拠事件(1979年)、アフガニスタンへのソ連侵攻(1979年)等、米国の威信を傷つける事件が次々と起こりました。経済面では、オイルショックによるインフレと不況を背景に、投資の低迷や規制の増加を受けて製造業の競争力が大きく低下しました。自動車をはじめとする工業製品で、「メイド・イン・USA」という言葉が、品質への疑問と同じ意味に使われ始めます。
そうした中、1970年代後半に米国は経常収支赤字の拡大とドル安に直面します。ブレトンウッズ体制下では経験していない状況です。なぜそのような事態に陥ったのでしょうか?
ブレトンウッズ体制下では、ドルの為替レートが固定されていますので、米国の経常収支が赤字になったとしても、それがただちにドル安につながるわけではありません。決済通貨としてのドルへの需要もあるので、各国でドルの買い支えが起こるからです。もちろん、各国が保有するドルの実質的な価値と、固定されたドルレートとの乖離が覆い隠せなくなったときに、危機(ニクソンショック)となりましたが、それまでは少なくとも表面的にはドルの為替レートは変動しませんでした。ところが、1970年代には変動相場制になっているため、ドルへの信認低下はそのままドルの為替レートに反映されて、ドルが暴落してしまったわけです。
価格が先行き一層下落すると見込まれる商品を、すぐに買う人は限られます。もう少し安くなってから買おうとする人が多いほど、今は売れ行きが悪く、今の価格も下がります。当時のドルも同じことで、今後もドル安が続きそうであれば、米国以外の国・企業は、当面必要なドル資金だけ借り入れておき、後日さらに安くなったドルを買うのが合理的です。経常収支赤字が増大し、ドルが国外に流出するにつれ、ドル安が続くとの予想が一層のドル安を招くことになりました。その悪循環を断ち切るため、カーター政権は空前絶後の思い切った手を打ちました。それに加えて、皮肉なことに米国自身の弱さが、ドル安反転の推進力ともなりました。
変動相場制の時代
固定相場制(さらには金本位制)の時代には、外貨準備高が減少してくると、好むと好まざるとにかかわらず、引き締め政策を採らざるを得ないのが通常です。日本では、「国際収支の天井」とも呼ばれました。天井が近づくと(すなわち外貨準備が一定の額まで減っていくと)、頭がぶつからないように姿勢を低くしなければいけない、というわけです。しかし、スミソニアン体制崩壊後の変動相場制下ではそうではありません。外貨準備が底をつく前に、経常赤字国の為替レートは下落して、赤字が自然に縮小するはずですから、経常収支の動向を心配して経済運営をする必要はないと信じられました。
しかも、1970年代には海外からの資本流入が容易になっていきます。特に、産油国が獲得したドル(オイルダラー)が欧州の銀行等を通じて大量に発展途上国への融資に回りました。経常赤字になっても、ファイナンシングが容易に行われる見込みがあれば、少なくとも相当の期間は、調整政策を考えずにすみます。主要国を含む各国は、国内の経済成長(より直接的には失業の減少)を主たるターゲットにした経済運営へと舵を切っていきます。安定を目指す経済運営の指針を「規律」と呼ぶとすれば、国際収支を基盤とする規律が政策運営上軽視されるようになったと言えるでしょう。
その結果、経済の潜在的な力を制約なく発揮できることになったと評価することは可能です。「国際収支の天井」が近づくたびにブレーキを踏まされたのでは、なかなかスピードも出ないでしょう。しかし同時に、この動きは、経済運営における政治の勝利をもたらしてしまう恐れをも意味します。というのも、経常収支をそれほど気にせず、政府・与党がなるべく好況を維持し雇用を増やすような拡張的な経済運営を行えば、結果的に自らの政治基盤の強化につながり、次の選挙でも有利になることは否定できないからです。こうして、変動相場制下で、海外からの資金借り入れが容易な状況においては、経常収支が赤字であってもそれを軽視するインセンティブが働くようになってしまいました。
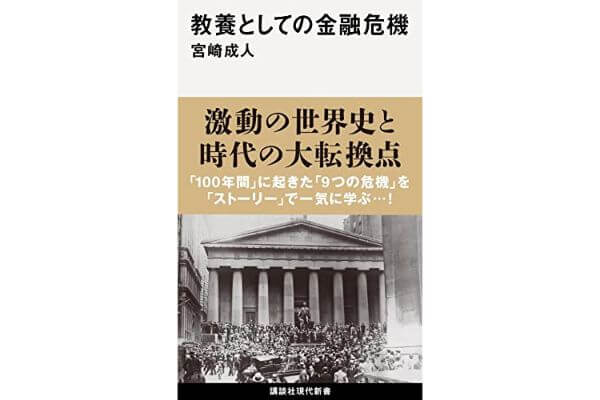
<著者プロフィール>
宮崎 成人
1962年東京都生まれ。1984年東京大学法学部卒業。1988年英オックスフォード大学にて国際関係論修士号(M.Phil)取得。1984年大蔵省(現・財務省)入省。主計官、国際機構課長、副財務官など歴任。欧州復興開発銀行(EBRD)日本理事室、金融安定化フォーラム(FSF)事務局での勤務を経て、2008~2016年国際通貨基金(IMF)アジア太平洋局及び戦略・政策・審査局審議役、2017~2021年世界銀行駐日特別代表。ロンドン、バーゼル、ワシントンなどで通算17年間海外勤務。2016年より、東京大学大学院(総合文化研究)客員教授。現在、三井住友信託銀行顧問。



