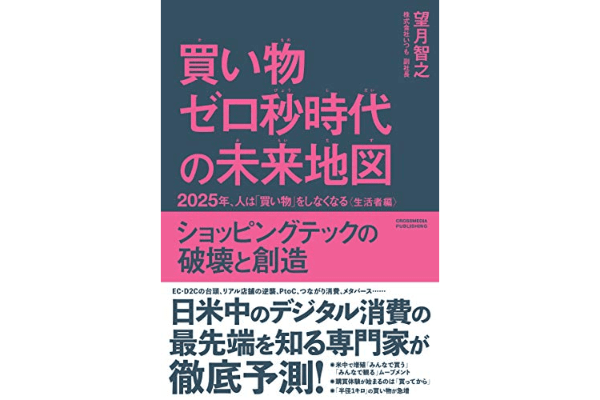『買い物ゼロ秒時代の未来地図――2025年、人は「買い物」をしなくなる〈生活者編〉』より一部抜粋
(本記事は、望月智之氏の著書『買い物ゼロ秒時代の未来地図――2025年、人は「買い物」をしなくなる〈生活者編〉』=クロスメディア・パブリッシング、2021年1月29日刊=の中から一部を抜粋・編集しています)
現実が映画『レディ・プレイヤー1』に追いつく
スティーヴン・スピルバーグが監督を務め、2018年に公開された『レディ・プレイヤー1』は、2045年の未来を描いたSF映画だ。主人公の青年をはじめ、この世界で生きている人たちは、1日のほとんどをVR(バーチャル・リアリティ)ゴーグルを装着して生活している。つまり、現実世界ではなく、VR世界で主に過ごしているのだ。
私は「これって実はもう現実化していないか?」と思いながらこの映画を観ていた。
もちろん、技術的な面は『レディ・プレイヤー1』ほどには発展していないし、どっぷりVR漬けという人もまだいない。現実世界の退廃感も映画ほどは進んでいない。しかし程度の差こそあれ、同じようなことができるところまでは来ている。すでにVRにハマっている人は、まわりにも確実にいる。
VRゴーグルも各社から発売されており、そのラインナップも増えてきた。Facebookが2020年10月に発売した「Oculus Quest2」は、前年に発売した従来モデルをさらに高性能化したもので、アプリやゲームの数も充実している。フィットネスや登山、宇宙旅行まで、すでにVRであらゆることが体験できるのだ。
VR会議のアプリもリリースされており、ビデオ会議が主流のテレワークも、いずれこちらに置き換わることは十分に考えられる。VRではユーザー同士の交流も可能であり、そうなると、もはやそちらの世界で学校に通ったり、仕事をしたりということが当たり前の世の中にもなるかもしれない。便利で面白いとなれば、現実世界よりもVRで過ごす人のほうが増えるのは当然の流れだろう。
すでに5Gもスタートし、大容量のデータ通信も可能な時代となっている。サービスが広がるまでには時間がかかるにせよ、現実世界も着々と『レディ・プレイヤー1』の世界に向かっているのだ。
VRの技術革新は、買い物にも多くのメリットをもたらす。
たとえばネットで野菜を買おうとするときに、おいしい野菜が届くかどうかはほとんど運だ。スーパーであれば、同じ野菜でも色や大きさを見ながら買えるが、オンラインではそれができない。今後、VR技術が進んで商品の質感もリアルに再現してくれれば、野菜のように一つひとつの状態が異なる商品も、自分の目で確かめてVRショッピングすることが可能になる。
また、服の試着は劇的にスムーズになる。いくら服が好きな人でも、リアル店舗にある服を全部試着することは不可能だ。しかしVRならそれも可能となる。着替える時間もゼロ。バーチャル店舗で気になった服をタッチすれば、瞬時にその服に着替えた姿になることができるので、ものの10分で店内のすべての服を試着することだって可能だ。
店員から声をかけられるのが苦手な人でも自由に試着ができるし、似合っているかどうか意見が欲しい場合は、バーチャル店員にチャットで聞けばいいのだ。
悪人も「善人にならざるを得ない」スコアリング
テクノロジーの進化によって、私たちの生活がより便利に、より面白くなっていくという話は、聞いているだけでもワクワクするものだ。しかし、そうした便利さと引き換えに、何かを犠牲にしていることもある。
たとえば今、スマートフォンを使って道路や施設の混雑状況、自分の興味のあるニュースなどをすぐに知ることができるのは、サービスを提供してくれる事業者に、私たちが位置情報や検索情報などを開示しているからだ。個人情報を提供したくないのであれば、こちらから送信しないことも選択できるが、そうするとそのアプリの機能をフルに活用することはできない。
個人情報が今よりさらに多く企業側に渡るとどうなるか。参考となるのが中国だ。
中国では「スコアリング社会」が進んでいて、個人の信用情報はアリババなどのプラットフォーマーが握っている。職業や資産、借入金の返済状況、消費の傾向、さらには交友関係までが「信用スコア」に反映され、スコアによりお金を借りるときの金利が変わったり、受けられるサービスが変わったりする。
あまりにスコアが悪いと、プラットフォームから退場させられてしまう。みんながスコアを気にしているがゆえ、「悪い人が減って善人が増えた」という人もいる。
日本人が利用しているアプリでも、このようなスコアリングがすでに行われている。
ウーバーイーツやメルカリなど、個人と個人をマッチングするようなアプリでは、ユーザーが相互評価する仕組みが備わっている。評価が低いとマッチングされにくくなるので、マナー違反やルール違反をシステムの面から防いでいるというわけである。
企業に渡る個人情報が増えることで、毎日必ずといっていいほど私たちの目に触れている「広告」も、効果がより高い場所に組み込まれる。たとえばECサイトで検索をすると、検索結果の一覧が表示されるが、そのものズバリの商品名で検索したのに、検索上位に競合他社の商品が出てきた場合は、広告の可能性がある。
こうした広告は、ユーザーが購入することを決める直前に、「あなたが欲しいA社の商品よりもちょっと値段は高いですが、健康志向のこちらの商品はどうですか」と、そっと耳打ちして、迷う瞬間をつくり出しているのだ。実はこの「迷う瞬間」というのは、デジタルシェルフ上においても広告価値が上がっており、今、私たちが無意識のうちに割り込んで入ってくるものがとても増えている。
従来のテレビCMは、いわば「生活者の決断からは遠い場所」で広告を打っていたが、今や生活者の決断場所は手元(スマートフォン)にある。広告はそこまで近づいてきているのだ。個人データが収集され、検索以外にもユーザーの「迷う瞬間」が解析されれば、こうした広告はもっと増えるだろう。
「モノを売っていない店舗」が増加する
第3章では、EC大国の中国で実店舗の出店がブームとなっている現象を解説したが、今後はその流れがほかの国にも広がっていくことが考えられる。
出店ブームを支えるのは、すでに述べたように「生活者の体験」である。今や商品はどれも低価格・高品質が当たり前だ。もはや生活者はそこに価値を感じておらず、「自分がその商品に触れることで、どんな体験ができるのか」に興味や関心が移り変わっている。
ECは便利だが、ただオンラインだというだけでは物足りないという生活者も増えている。そのため、店舗で何かが体験できることと、その体験がデジタルと融合していることが、2020年代の店舗のトレンドになるだろう。
そのような店では、モノを買うことも基本的にはない。なぜなら、デジタルが浸透した世界では、「体験してもらうこと」が目的だからだ。
たとえば、そこで新商品を使ってみた、試着してみたといった体験を、SNS上に載せる。ここ数年、日本でもインスタ映えを狙った店舗が増えたが、今後はそうした体験を共有する流れがさらに加速していくだろう。
店内のどこを見回しても、商品が棚に置かれていないということも珍しくなくなる。そこにはただオンラインへと誘導する案内があるだけだ。
「もっと詳しく知りたい方はこちら」「この商品のカラーバリエーションはここから見られます」店舗ではこのような案内だけにとどめて、デジタルシェルフ化を進めていけば、店舗は在庫を抱える必要がなくなる。
第3章では、店舗は「倉庫型」と「体験型」が生き残るという話を述べたが、両者は相反する流れである。ただ、両極化が進むことで、店舗の役割はさらに明確になっていく。これからの10年間は、従来型店舗が次々に閉店するが、店舗そのものはなくならない。なぜなら、今の私たちに必要な「新しいタイプの店舗」もまた続々とオープンするからだ。
Eコマースに勝てるのは小商圏ビジネスの店舗
では、従来型の店舗はすべて消えてしまうのかというと、そうではない。EC化が進む中で、従来型のまま生き残る店舗も当然ある。
ただし条件がある。それは前章でも触れたように、「小商圏で展開している」こと。小商圏の店舗には、「モノがすぐに手に入る」という、ECにはない強みがあるからだ。
小商圏とは、一般的には半径1〜2キロ圏内を商圏とする店舗のことだ。「徒歩10分以内」、地方なら「車で10分以内」と言い換えてもいいだろう。
日本のほとんどの地域は、この10分圏内に、コンビニ・スーパー・ドラッグストアなど、生活必需品を売っている店舗がある。海外では、どこにでもこのような店舗があるわけではないので、これはある意味、日本の特色ともいえる。
こうした店舗では、ワンストップで生活に必要なものすべてを揃えることができる。いずれはAIによって、生活必需品が必要なタイミングで自動的に送られてくることは考えられるが、まだその展開に進むまでには時間がかかる。しばらくの間、小商圏の店舗は私たちに欠かせないものであり続けるだろう。
2020年のパンデミックでも、マスクやトイレットペーパーなど衛生用品の一部が一時的に在庫切れになることはあったが、生活できなくなるほど困りはしなかった。食料品は買いだめこそあったものの安定供給されていたし、赤ちゃんのミルクやおむつも品切れにはなっていなかった。これも小商圏に店舗があったからだ。逆に在庫の少ないECサイトからは、そのような生活必需品が消えることも少なくなかった。
日本は台風や地震などの災害も多く、物流がストップすることも珍しくない。そんなときに、ECはほとんど機能しなくなるが、リアル店舗ならば少なくとも在庫の分だけは商品の供給を続けられる。生活者からすれば、そういった理由からも「店舗は残ってほしい」と思うところだろう。
小商圏の店舗が少ないアメリカでは、住宅街でギグワーカーが活躍中だが、日本では、自宅から10分圏内に十分な数の店舗があるので、まだアメリカのような激しい配達競争は起こっていない。ウーバーイーツなどの浸透によって、だいぶ競争が進んだようにも思えるが、自宅から10分圏内に店があるという強みはそれだけ大きいものなのだ。
望月智之(もちづき・ともゆき)
株式会社いつも 取締役副社長
東証1部の経営コンサルティング会社を経て、株式会社いつも を共同創業。
同社は消費財ブランドに対するD2C・ECコンサルティング会社として、現在までのべ9500案件以上を支援し、2020年12月には東証マザーズ上場。
自らはデジタル先進国である米国・中国を定期的に訪れ、最前線の情報を収集。
デジタル消費の専門家として、消費財・ファッション・食品・化粧品のライフスタイル領域を中心に、ブランド企業に対するデジタルシフトやEコマース戦略などのコンサルティングを手掛ける。
番組ナビゲーターを務めるニッポン放送「望月智之 イノベーターズ・クロス」のほか、J-WAVE、東洋経済オンライン、ダイヤモンド・オンラインなど、メディアへの出演・寄稿やセミナー登壇など多数。
著書に『2025年、人は「買い物」をしなくなる』がある。
『買い物ゼロ秒時代の未来地図――2025年、人は「買い物」をしなくなる〈生活者編〉』